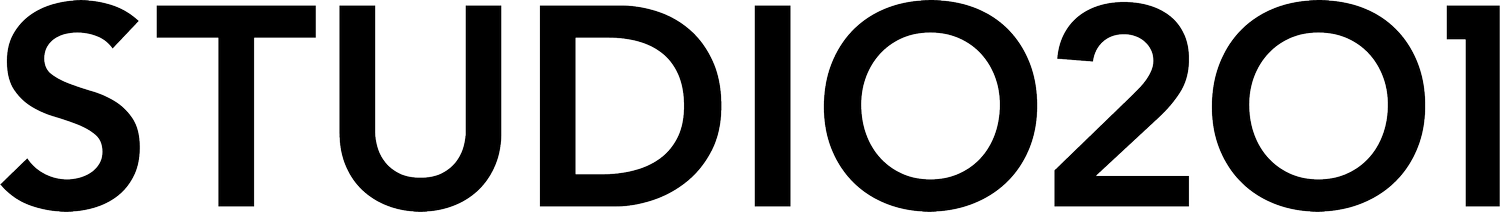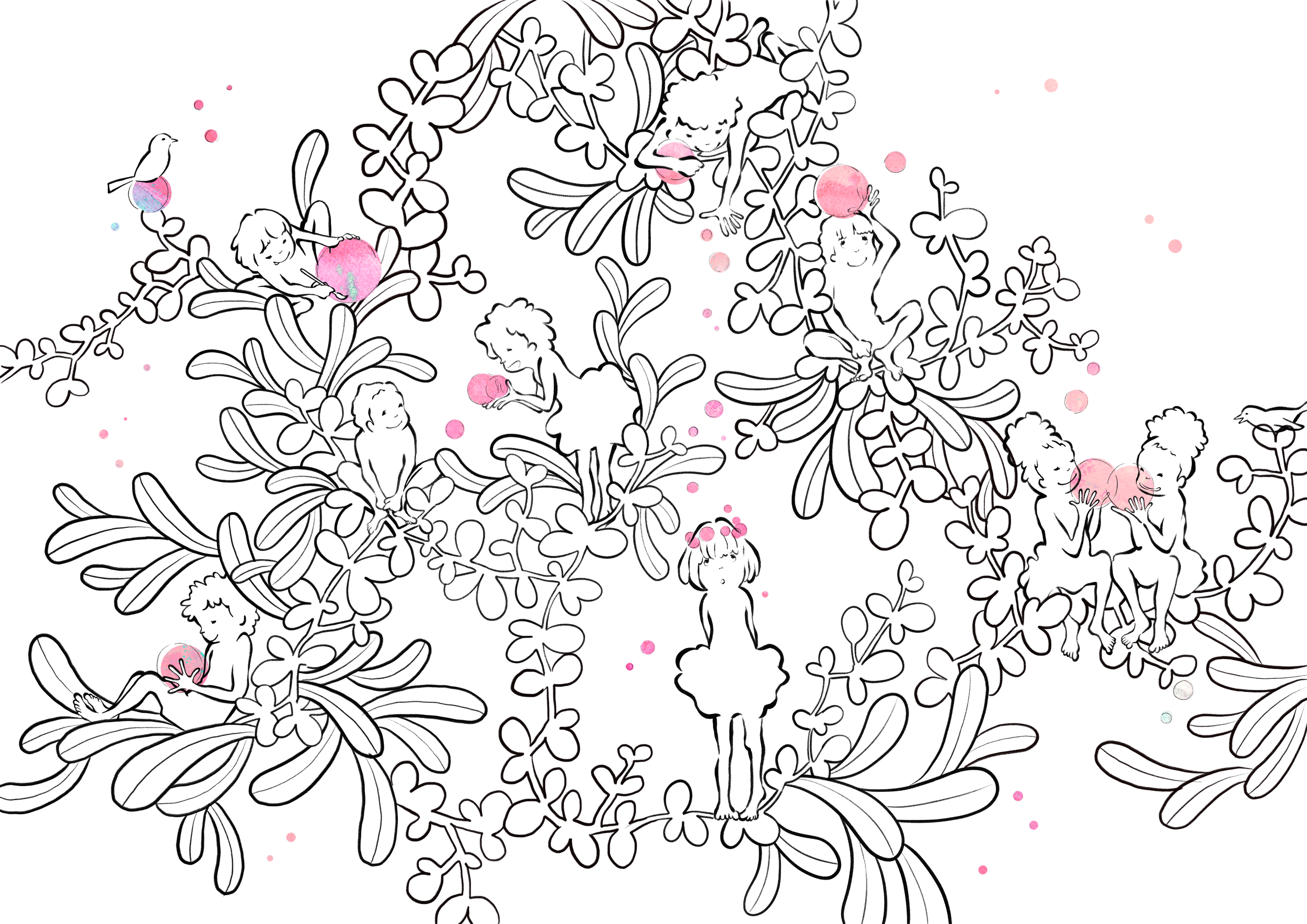MESSAGE
代表の想い
今、私には何ができるのか
2017年、7年間の海外生活を終え日本へ帰国したとき、私を包み込んだのは漠然とした閉塞感でした。
ある財団の調査で目の当たりにしたのは、日本の若者たちの衝撃的な現状です。「自分を大人」「責任ある社会の一員」と考える日本の若者は、私が暮らしていたカナダのわずか3分の1から半数程度。さらに「自分で国や社会を変えられる」と考える人は18.3%にとどまり、諸外国と比べても際立って低い数字でした。
この自己肯定感の低さは、当時40歳を目前にしていた私たち大人世代が、日本の若者に希望を示せなかった結果だと感じました。
そして同時に、責任ある大人だと思っていた私たち自身も、彼らの姿を映す鏡なのかもしれない。
社会に対する強い危機感と、自分たちの責任を痛感した瞬間でした。
もちろん、画一的な評価基準に押し込められ、近視眼的な「結果の大小」に翻弄される社会のあり方にも課題があります。「タイパ」「コスパ」など効率を優先する価値観が浸透する中で、人は次第に外からの評価や動機に慣れ、自分自身の軸で決断することに不安を抱くようになっているのかもしれません。
しかし、本当に大切なのは、たとえ小さくても自分が正しいと信じることを、「できることを、できる範囲」で行動に移すこと。
その想いを胸に、「自分には何ができるのか?」と模索し始めたのが、まさにこの時期でした。
アートとの出会い
そしてSTUDIO201の誕生
きっかけは2020年、コロナ禍で保有するビルのテナントが撤退した際に訪れました。その壁面にアーティストの鈴木掌(すずき・つかさ)氏にウォールアートを描いていただく機会を得たのです。
真っ白な壁に次々と描かれるフクロウの絵。その光景を目の当たりにしたとき、私は言葉にできないほどの衝撃を受け、アートに宿る無限の可能性を感じました。
正解のない問いに対し、自分なりの解釈でかたちにしていく姿。
個性や多様性とは、他者との比較ではなく、自分自身を深く探究したその先に現れるもの。
「自分は自分でいいんだ」と体現するアーティストの姿に深く魅了され、実家跡地の201号室を開放。シェアアトリエとして活用したのが、STUDIO201の始まりです。その名前には、西武池袋本店8階にかつて存在し、新しいカルチャーを発信し続けた伝説の場所「スタジオ200」へのオマージュも込めています。
「寛容」を体現した、
忘れられない二つの出来事
私には2人の子どもがいます。長女と長男です。
2018年、長男が2歳のとき、「グルコーストランスポーター1欠損症(指定難病248)」という難病を患っていることがわかりました。この病気は、糖質代謝異常で、糖質(炭水化物)を摂取しても脳に栄養が届かず、発達の遅れや言語・運動障害などを起こすものです。
薬や根本的な治療法はなく、唯一の対処法は糖質制限を伴う非常に厳しい食事療法です。体内の糖質を常に枯渇させ、脂質をケトン体に変換し、栄養として脳にを届ける必要があります。
現在(2025年時点)は、1日あたり糖質15g以下、脂質122g以上という厳密な栄養バランスを守らなければならず、口にするすべての食材を、一つひとつ計量して調理しています。
診断当初には、この食事療法を毎日続けられるかという大きなプレッシャーを感じ、そこはかとない不安を覚えました。また、息子が話したり歩いたりすることさえ難しいかもしれないと知り、深い悲しみに暮れました。
しかし、この7年間、妻は毎日欠かさず、365日3食とおやつ全てを計算し、調理し続けてくれました。
そのたゆまぬ努力のおかげで、長男は今、元気に自分の足で歩いて学校に通っています。
“普通”と少し違うのは、市販食品を原則使うことができず、外食も極めて難しいこと。
そのため、旅行を計画する際も、キッチンのない一般のホテルには宿泊できず、旅先での食事にも常に制限が伴います。調理環境が整っている場所を前提に、綿密に準備された食事を持参しなければなりません。
私たち家族にとって ”旅行" とは、旅先で温泉やごちそうをゆっくり楽しむ、ということではありません。
そんなある日、あるホテルに勤める友人にこの事情を伝えたところ、「ホテルのレストランに必ず対応させるので、ぜひ宿泊に来てほしい」と言ってくれ、完璧な対応をしてくれました。
そのおかげで、長男の診断を受けてから初めて、調理の心配をせずに “普通の旅行” を楽しむことができたのです。
また、ある年の長女の誕生日に、彼女から「テーマパークのホテルに泊まりたい」とリクエストを受けました。
親としては叶えてあげたい気持ちがありながらも、長男の食事のことが頭をよぎり、すぐには決断できませんでした。
それでも思い切ってホテルに事情を相談したところ、快く食事対応を引き受けてくださいました。
どこへ行っても、私たちが用意したお弁当箱からしか食べられなかった長男にとって、皆と同じタイミングで、同じ食器で食事をとれることは、かけがえのない経験でした。
さらに、コンビニや外食で “ふらっと何かを買って食べる” という当たり前のことができない彼にとって、それは人生で初めての “キャラごはん” でした。
満面の笑みを浮かべながら食べているその姿に、私たちも思わず涙してしまいました。
そのとき、厨房から出てきたシェフがこう言ってくれたのです。
「私は料理人ですから、料理を作ることしかできません。でも、こんなことでよければ、またぜひ来てください。」
笑顔で仰ってくれたこのシーンは今でも鮮明に覚えています。
長男にとって食事とは、単なる栄養補給でしか無いと諦めていた私たちにとって、この経験は食の喜びを提供できるという、一筋の希望の光に見えました。
シェフにとっては、些細なことだったかもしれません。
ただし、たとえ些細なことであっても、目の前のできごと一つ一つに真摯に向き合うことで、それが誰かにとっては深い意味を持つことがある。
STUDIO201が考える「寛容」とは、他者を受け入れるだけでなく、「分かち合う」こと。
友人やシェフの行動は、自分の「できることを、できる範囲で」差し出してくれた、まさにその体現でした。
「たいまつの火」は、受け取った人も、差し出した人も、心がほっこり温まります。
そんな小さな成功体験を提供し続けることで、暗くて不安な「自己探究の旅」に、小さな灯火をともしたい。
自分の中に太くて深い根をはり、自己肯定感に裏付けられた自信を持てるようになった人は、きっとまた次の誰かに「たいまつの火」を差し出す。私はそう信じています。
そんな人たちであふれる、「豊かで寛容な社会」を夢見て、STUDIO201を立ち上げました。
2025年7月
STUDIO201代表
宮副信也